ネタバレを含みます。知りたくない方はご注意ください。
「翼を持ったものには腕がない」「腕がある者には翼がない」
1989年に発表された山岸涼子さんの「牧神の午後」はもう30年以上前の作品です。
「しかし神は残酷なほどに公平だった」
芸術の才能(大きな翼)を持った代わりに、日常を生きる器用さ(腕)は持ちえない、なのに両方を望んだ結果
「ニジンスキーは自己の世界へ飛翔してしまったのだ」
という結果になりました。
自己の世界へ飛翔は、発狂を指す言葉です。
芸術を極めるためには不幸でありつづけなければいけないのか?という議題も巻き起こしたこの作品を、私なりに考察しました。
「牧神の午後」あらすじ

ロシアの天才バレエダンサーヴァーツラフ・ニジンスキーの半生を、ミハイル・フォーキンの視点で描かれたもの。
「翼を持ったものには腕がない」
バレエの舞台が始まる直前に雰囲気が変わる、顔が変わる、まるで憑依したかのように。身体機能を超えたかのような跳躍。観客を巻き込み完全陶酔するステージといった、踊るための「翼を持つ」。
一方で、人とのコミュニケ-ジョンも上手くとれない日常生活が困難な「腕がない」状態。
器用な腕を持つ敏腕マネージャーの支援を受けていた時は、翼を活かしバレエに没頭出来ていたニジンスキー。
だが、ニジンスキーの結婚を「裏切り」と判断したマネージャーは彼の元を離れてしまった。
器用な腕をなくし、翼だけではバレエでの生活も出来なくなり最後には発狂してしまう。
ニジンスキーの気質は?

強烈なエンパスです。まごうことなき受信型です。
この作品でいうところの
- 大きな翼=エンパス(受信型)の感覚を極めたもの
- 器用な腕=エルゴン(送信型)の感覚を極めたもの
と、考察出来ます。
生まれ持った受信型・送信型の感覚を成長させて使えるようになると、それぞれ以下のような特徴・得意分野を持つようになります。
エンパスの特徴
- エネルギーを感じることや思考に使う癖があります。
- 一瞬の全力集中であっという間に燃え尽きます。
- 人をフォローするのが得意です。
- 物事を他人起点で見ます。
- 場の空気を読むのが得意です。
- 名監督になれます。
- 第4チャクラ(HSP)か第6チャクラ(エンパス)を中心に使います。
- 理論・感覚が優先です。
- その場によって変化し、顔つきまで変わります。
- 模写が得意です。
- 「時」とは一瞬で移り変わる、セル画(完成された一枚絵の連続)の概念です。
エルゴンの特徴
- エネルギーを行動・実行に使う癖があります。
- そこそこの集中力を長期間持続させられます。(半年~黙々と集中するイメージ)
- 自分が先だって動くのが得意です。
- 物事を自分起点で見ます。
- 場の空気を作るのが得意です。
- 名選手になれます。
- 第2・第3チャクラを中心に使います。
- 行動・実践が優先です。
- どの場所でも、自分自身を持っています。
- オリジナリティを出すのが得意です。
- 「時」とは動き続けて経過していくもので、動画の概念です。
「翼を持ったものには腕がない」「腕がある者には翼がない」
受信型と送信型の感覚は男女のように明確に分かれます。
なので両方を持つことはありません。


ニジンスキーが「自己の世界へ飛翔してしまった」理由の考察

ものすごく簡単に書けば、
人として成長していくための試練を乗り越えられなかったから
です。以下もう少し詳しく書いていきます。
人が成長していく仕組みや法則を解説するものとして、発達理論があります。
発達していく経過を発達段階として説明します。学校でいう所の、今は小学一年生・高校二年生、みたいな感じです。
発達段階を進んでいく上で、
- マズローの五段階欲求なら「自己実現欲求」
- インテグラル理論なら「ティール段階」
という、個を超える段階があります。
何かを極める直前などに、この段階へ進むための試練・壁が訪れます。ニジンスキーはバレエを極めていく過程で、この段階へ進もうとしていたと考察できます。
このような試練がやってくるというのは発達心理学で解説された話です。「こういうものだ」と納得するしかない仕組みのようです。
この段階の試練は以下のようなものです。
- 自分の価値観をくつがえすほどの衝撃体験
- 全てを失うような出来事
- 生死の保障もない危機的な状況
この体験をすれば、人が進んでいく道は3つです。
- 気が狂う
- ひねくれて悪の道へ進む
- 乗り越えてティール段階に進む
ニジンスキーはこの中の
1.気が狂う の状態に進んだと考えられます。
この進む3つの道は、現実へどう対処したかも関係します
- 気が狂う:現実からの逃避・拒否
- ひねくれる:現実を歪める、都合が良いように解釈
- 乗り越える:現実をしっかり見て対峙
ニジンスキーは、現実逃避しました。
翼と腕の両方を望んだから影に捕らえられた(=発狂)のではなく。両方を望んたことで訪れた試練から逃げた結果として影に捕まりました。
つまり、ささやかな幸せを望んだから発狂したのではない、ということです。
このことから、
- Q:芸術を極めるためには不幸でありつづけなければいけないのか?
- A:不幸の経験は必要かもしれないが、ずっと不幸である必要はない
と、私は考察しています。
ティールへ向かう試練は、「狂う」ぐらいのことをしなければ逃げられません。
狂わないためにニジンスキーがするべきは、現実と向き合うことだったと思います。現実と向き合い乗り越えればさらに感性が磨かれていたはずです。
- 飛べるような気がしたから飛べた→現実に飛べたからOK
- 舞台で自らを慰める→理解できない観客が悪いのか?伝えられない彼が悪いのか?
- 振付けを教えても伝わらない→伝わる方法を模索する必要があるのでは?
- バレエを考えるでなく感じる→深め、高めるためには「考える」「感じる」の両方が必要
このあたりからも現実離れした、言い換えれば芸術肌な面がうかがえます。
これについては作中にも
「いつまでも規制の事実にとらわれないということは ひいては現実を習得できないという事なのだ」とあります。
「そのかわり喜びも恐怖もその時その時はじめてのように新鮮に味わえるーこの新鮮さをいつまでも味わえる感受性こそがニジンスキーの才能であり光を発する源である」
ともあります。
この考察はあくまでもニジンスキーが狂った理由へのものなので、彼の感性を否定しているわけではありません。
「狂わないまま感性を高める方法はあったのか」の考察

私は希望的観測を込めて「あった」と考察します。
ただし、高さ・鋭さのトータルが同じくらいという意味で、同質のものではないことをご理解ください。
方法は2つです。
- 感性を支える台を強くして感性自体も大きくする
- インナーチャイルドを成熟させ、コントロール不能な赤子→赤子の感性を活かす
以下解説していきます。
1.感性を支える台を強くして感性自体も大きくする
感性が強すぎて自分が支えきれる量を超えれば潰れます。台が強く成れば、それに伴って感性も高まります。
- 体力を付ける:健康になる
- 心を強くする:自分を好きになる
- 精神性を高める:現実と対峙する
これにより、感性を安定させ、さらに大きくなります。
2.インナーチャイルドを成熟させ、コントロール不能な赤子→赤子の感性を活かす
ニジンスキーの母親が訪れてきた時、丁寧に出迎えるニジンスキーと、それを無視する母親というシーンがありました。
ここから、ニジンスキーの中のインナーチャイルドが想像・推測できます。
インナーチャイルドは「泣いている心の中の子ども」という部分です。
自分の中のインナーチャイルドは、成長はしませんが成熟させられます。
インナーチャイルドの年齢を上げることは出来ないけれど、その年齢で成熟させる形です。「泣いている子ども」から「生きることを楽しむ子ども」への変化です。
成熟した子どもが自分の中にいるのは相当な強みです。
子どもの自由な発想や感性を、大人である自分と上手く連携させ現実化させられます。
まとめ
一瞬で消えるのは美しいかもしれないけれど、感性を大きくすれば、その一瞬の輝きよりも大きな光を持続させられると思っています。






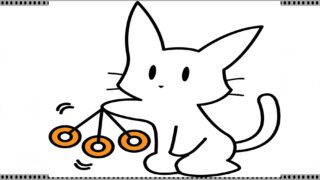














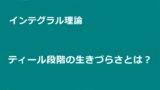
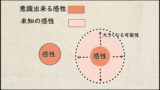


あくまでも、山岸涼子さんの作品「牧神の午後」の登場人物としてのニジンスキーへの考察であることをご留意ください。